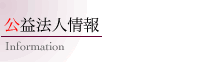令和7年度第2回公益社団法人京都染織文化協会セミナー
日本のファッション文化─衣服と装飾の発展 シリーズ⑳─
『 歌舞伎よもやま話 〜江戸時代の文化にふれて〜 』
受講者の募集を締め切りました
江戸初期に出雲阿国という女性がはじめた「かぶき踊り」が、のちに男性が女形を演じて演技や演出に磨きがかかり、やがて総合舞台芸術へと昇進した『歌舞伎』。歌舞伎は、さまざまな工夫によって幕府の禁圧を乗り越え、江戸時代の町人文化に支えられて発展を続けてきました。 今回のセミナーは歌舞伎役者 中村鴈治郎氏を講師にお迎えし、歌舞伎が総合舞台芸術となった歩み、衣装や隈取に込められた意味などについてお話いただきます。歌舞伎を通して江戸時代の文化を学ぶ機会として開催しますので、皆様の参加を心よりお待ち申し上げます。
(講師)
なかむら がんじろう中
 村 鴈治郎 氏 (歌舞伎役者)
村 鴈治郎 氏 (歌舞伎役者)
*プロフィール*
1959年2月6日生まれ。四代目坂田藤十郎の長男。67年11月歌舞伎座『紅梅曾我』の一萬丸で中村智太郎(ともたろう)を名のり初舞台。90年名題適任証取得。95年1月大阪・中座『封印切』の忠兵衛ほかで五代目中村翫雀を襲名。2015年1・2月大阪松竹座『廓文章』の伊左衛門ほかで四代目中村鴈治郎を襲名。
1969年1月『大商蛭子島』の箱王丸で、同年11月『椿説弓張月』の為朝の子為頼で国立劇場特別賞。83年重要無形文化財(総合認定)に認定され、伝統歌舞伎保存会会員となる。
88年、98年、99年に十三夜会賞奨励賞。99年関西・歌舞伎を愛する会演技賞。2006年度日本芸術院賞。同年11月『元禄忠臣蔵』の富森助右衛門で、09年10月『京乱噂鉤爪(きょうをみだすうわさのかぎづめ)』の鶴丸実次で、13年11月『伊賀越道中双六』の雲助平作で国立劇場優秀賞。11年第32回松尾芸能賞優秀賞。15年度第34回京都府文化賞功労賞。18年9月『傾城反魂香』の又平と『吉野山』の忠信で、ロシア連邦文化省文化功労賞。19年紫綬褒章。日本芸術院会員。
1959年2月6日生まれ。四代目坂田藤十郎の長男。67年11月歌舞伎座『紅梅曾我』の一萬丸で中村智太郎(ともたろう)を名のり初舞台。90年名題適任証取得。95年1月大阪・中座『封印切』の忠兵衛ほかで五代目中村翫雀を襲名。2015年1・2月大阪松竹座『廓文章』の伊左衛門ほかで四代目中村鴈治郎を襲名。
1969年1月『大商蛭子島』の箱王丸で、同年11月『椿説弓張月』の為朝の子為頼で国立劇場特別賞。83年重要無形文化財(総合認定)に認定され、伝統歌舞伎保存会会員となる。
88年、98年、99年に十三夜会賞奨励賞。99年関西・歌舞伎を愛する会演技賞。2006年度日本芸術院賞。同年11月『元禄忠臣蔵』の富森助右衛門で、09年10月『京乱噂鉤爪(きょうをみだすうわさのかぎづめ)』の鶴丸実次で、13年11月『伊賀越道中双六』の雲助平作で国立劇場優秀賞。11年第32回松尾芸能賞優秀賞。15年度第34回京都府文化賞功労賞。18年9月『傾城反魂香』の又平と『吉野山』の忠信で、ロシア連邦文化省文化功労賞。19年紫綬褒章。日本芸術院会員。
(日時)
令和8年 3月 4日(水)15:00〜17:00 (受付14:30〜)
(会場)
からすま京都ホテル2F 双舞の間(烏丸通四条下ル℡371-0111)MAP
(参加料)
無 料(事前申込制)
(定員)
80名
(受講申込方法)
下記いずれかの方法によりお申込み下さい。
定員に達しましたので申込みを締め切らせて頂きました。ご了承ください。