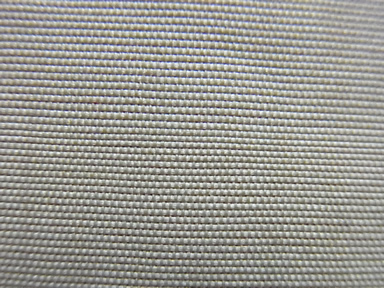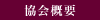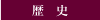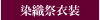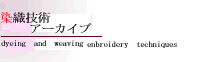ûÑ@@ËèÊ«
uûÜvÆàBo
ɶ
AÜ
Éû
ðgÁ½½D̦D¨B¬³Ìn¿ÆµÄº¬ãAÀyRãɽp³ê½ªA]ËãÉÍkÉAãdqÌZpªm§µÄlCðµAn¿ÍÙÚ®SÉkÉAãdqÉÚsµ½B
}¬ÉÞµ½ûÑÆ»ÌZpÍAõDߪ³³ê½ºa6`8NÜÅÍp³³ê§ìàÂ\Å Á½±Æªf¦éªA»ÝÍZpp³ª³êĢȢ½ß§ì³êĢȢB
@
@
ûÑͱÌæ¤ÈõDßÉ©íêĢܷ@¦NbNÅeßÌy[WÉWvµÜ·B
 |  |  |  |  |  |
| ¨TbÔH¶lÅ| |
¸F¶lº
|
¨Ô˶lÅ| |
iÖÔ¶lº
|
îÊeËÜ}¶lº
|
i}÷¶lº
|
 |  |  |  |  |  |
| §O¼|~¶l¨º
|
¨¼çHîÊ}÷¶l¬³ |
ÛäU¶l¼çH¨º
|
¡iöÏ¢
§O¶l¬³ |
s¼`lGÔ¶l¬³ |
¨¼çH»`Ëe¶lÅ| |
 |  |  |  |  |  |
| ¡Ø¶lº
|
iÖáÖ¼Ôj¶l¬³ |
i¶lº
|
¼çHcîg¶l¬³ |
iõ¼çH¶l¬³ |
ÎôæÔ¶l¬³ |
 |  |  |  |  |  |
| iqD¶¬³ |
C¼äDåÝ | ÷¶l¬³ |
_`繶líß |
÷äiDíß |
H¶líß |
 |  |  |  |  |  |
| iqDq¶låÝ |
iqD¬³ | gt¶låÝ |
iD¶l¬³ |
iqDÖÑ |
b¶lÖÑ |
 |  |  |  |  | |
| iDÖÑ |
gt÷¶låÝ |
Égt¶låÝ |
iDåÝ | g¶låÝ |
|
| | | | | | |
| | | | | |
|
@
@
@
@